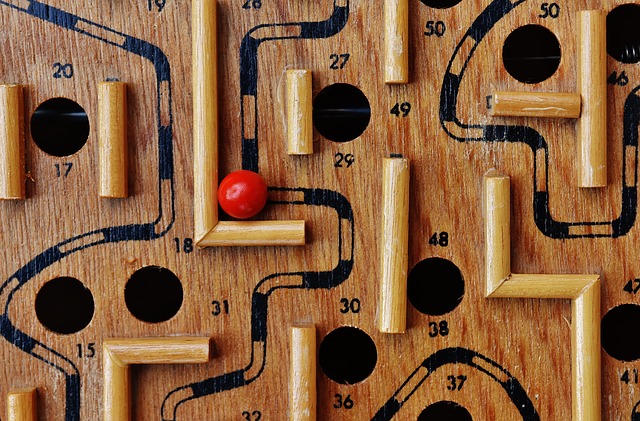こんにちは、AI-amの星山まりんです。
こんにちは、AI-amの星山まりんです。
「学校に行かなかったからできないこと」ってあるでしょうか。さしたることはありません。
「学校に行かなかったらこうなる」という決まった話もありません。
「学校に行ったらこうなる」という結果が、学校に通ったひとたち全員に適用されないのとおなじように。
もくじ
「学校に行かなくても今はいいと思うけれども、あとになって困るんじゃないか」
不登校の子どもさんがいる親御さんのなかには、
「学校に行かなくても今はいいと思うけれども、あとになって子ども自身が困るんじゃないか」
と考える方がたくさんいますね。
学校そのものに関してはこれまでの固定概念を切り離すことができても、学校生活のなかで得ること(勉強、社会性etc)や、「学校に行っていなかった」という事実が残ることをも切り離すことはできない、みたいな状態です。
そういうとき親は、「学校に行かないことで今後が大変になるということを教えてあげたほうがいい・頭に入れてあげたほうがいいのでは」とも考える。
子どもの年齢が低ければ低いほど、「子どもはまだそういうことがわかっていないから」と。
不登校にならなかった親は、不登校になった子どもになにをおしえられるのか?
もし子どもにそれらを教えるとして、親はなにを教えられるんでしょう。
「学校に行かなかったらこうなる」という決まった未来はないのに。
ましてや、たいていの親は、自分の経験談を話せるわけでもない。
話せるとすれば、マスコミから受け取ったイメージと、聞きかじった話、自分の不安がもとになってキャッチした情報や、よくて身内まわりの話、そんな程度であることが多いと思う。
学校に行って、勉強をしてきたひとが、「それらをしなかったときのこと」をどうして子どもに教えられるんだろう?
説得力のなさと「個人差」
行ったことのない国について話をすることはできません。
できてもそれはテレビで観た景色のこと、読んだ本に書かれてあった歴史のこと、ニュースで聞いた治安のこと、等々、そんなくらいのものです。
たとえ相手にその国へ行ってほしくなかったとしても、行こうとしている相手を、相手の心を動かすことはむずかしい(現地にいるひとに「来ないほうがいいよ」と言われたら、ちゃんと話を聞きもするだろうと思う)。
106歳の女性が、1日に3本のドクターペッパーを飲んでいるけれどいたって健康で生きている、という話もありましたね。
野菜を肉を魚をバランスよく食べ、お砂糖も添加物もとらずにいたとしても、全員が必ず健康に100年以上を生きるとはかぎりません。
いわゆる、「個人差」というやつ。ましてや子どもがのちにどうなるか、は口に入れるものが身体にどう影響するかよりもよほど、自分次第で結果を変えやすいものです。
親はなにを知っているのか?
学校に行っていても友だちがいない子どもはいるし、ニートになる子どももいます。
学校に行っていなくても友だちがたくさんいる子どもはいるし、年収1000万円を得るようになる子どももいるし、サラリーマンになる子どももいる。もちろんニートになる場合もある。
いずれも「学校のおかげ/せい」ではなくて、自分次第(=家庭次第)です。
占い師の言うことでさえ、わたしたちは半信半疑で聞く。
「あそこに行くと人生が変わるよ」と大勢が言ったところで、行ったけど変わらないひともいる。
「子どもだからまだ知らないけれども、自分は知っている」って、いったいなにを知っているんだろう。