広島・長崎に原爆を落としたアメリカ。
仮に「戦争を終わらせ、日本人の命を救った原爆投下を祝う式典」を日本で行うとなったら、わたしたちはどうするんだろう? どんな感情が湧くんだろう?
アメリカが主導した、1999年のNATO軍によるユーゴスラビア空爆から20年が過ぎました。
その空爆行為による介入を祝う式典が、2019年6月12日、コソボの首都プリシュティナで、ビル・クリントン(99年当時米国大統領)とマデレーン・オルブライト(99年当時米国国務長官)を招き行われたのでした。

NATO軍の介入を祝う? 空爆行為を祝う?
国際連合の決議を経ずに軍事介入したオルブライトをも招いて?(2019年6月12日、この日オルブライトの銅像が披露される)
euronewsによる記事「Kosovo marks 20 years since NATO forces arrived」
2007年につづき、2019年12月〜2020年1月に、よっぴーまりんで訪ねた旧ユーゴの旅で、わたし(よっぴー)自身がコソボで感じたことを書いています。
(トップの写真は、コソボの首都プリシュティナ、ビル・クリントン通りにある、ビル・クリントン元米国大統領の銅像と垂れ幕)
もくじ
2度生まれ、2度死ぬ「第1のユーゴ」と「第2のユーゴ」
ユーゴスラビアを牛耳っていたチトー大統領と、臨床心理学界を牛耳っていた河合隼雄さんは似ているなとおもう。
両者は、良くも悪くも、問題を権力で抑え一つの世界にまとめることができるカリスマです。
だけど、こういった力がある人たちの死後というのは、そのカリスマに勝る者がいない限り分裂は避けられず、よりいっそう狂気が深まるんですよね。
ユーゴスラビアの狂気について書く前に、概略を説明します。
(狂気については後編で書いていきます)

バルカン半島に位置する旧ユーゴスラビア。
国家としてのユーゴスラビアは、2度生まれ、2度死んだ、といわれています。
1度目は1918年12月、第一次世界大戦後、ユーゴスラビア王国 が建国されました(「第一のユーゴ」と呼ばれる)。
しかしながら第二次世界大戦でナチス・ドイツの侵攻にあい、1941年4月に分裂・占領され消滅してしまいました(後述の『ユーゴスラビア紛争へ〜ウスタシャとクロアチア独立国』参照)。
2度目は1945年11月、社会主義にもとづく連邦国家として再建。こちらが「第二のユーゴ」と呼ばれるものです。
国家名をユーゴスラビア王国からユーゴスラビア連邦人民共和国へと変えて歩みはじめ、1963年には ユーゴスラビア社会主義連邦共和国(構成国は後述、ならび上記地図参照)に改称されます。
この 第二のユーゴの主導者が、共和国・民族間の対立や混乱を抑えた終身大統領の ヨシップ・ブロズ・チトー です。

1980年5月にチトーが亡くなると、カリスマを失った国家体制は崩壊へ向かいます。
共和国・民族間の対立や混乱は息を吹き返し、1992年1月のスロベニア、クロアチア両国の独立承認により、第二のユーゴも幕を閉じ、ユーゴスラビア国家は解体されました。
ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国
1992年に解体されるまでの ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国 は、
北から
- スロベニア社会主義共和国(現在/スロベニア共和国、通称スロベニア)
- クロアチア社会主義共和国(現在/クロアチア共和国、通称クロアチア)
- ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国(現在/ボスニア・ヘルツェゴビナ)
- セルビア社会主義共和国(現在/セルビア共和国、通称セルビア)
- モンテネグロ社会主義共和国(現在/モンテネグロ)
- マケドニア社会主義共和国(現在/北マケドニア共和国、通称北マケドニア)
6つの共和国 と、
- ヴォイヴォディナ社会主義自治州(セルビア共和国内)
- コソボ社会主義自治州(現在/コソボ共和国、通称コソボ)
2つの自治州 でした。

[box class=”yellow_box” title=”現在のコソボ共和国について”]
2019年11月時点において、旧ユーゴのうちコソボのみ、国連加盟国の半数近くにのぼる世界85カ国が承認を拒否しています(セルビアをはじめ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ロシア、中国、スペイン、イスラエルなど)。
一方、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本など93カ国からは独立承認を受けています。
将来的に国際社会から一致した承認を得られるかどうかは未だ不透明な状況で、コソボの独立を承認していない国々は、コソボを国連の管理下にあるセルビアの一部として取り扱っています。[/box]
ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の多様性
民族構成の複雑さから「人種のモザイク」と呼ばれたユーゴスラビア社会主義連邦共和国(以下、ユーゴ。またはユーゴ連邦、旧ユーゴ)は、その多様性を表現するのに、
7つの国境
6つの共和国
5つの民族
4つの言語
3つの宗教
2つの文字 を持つ
1つの国家 と言われます。
[box class=”blue_box” title=”人種のモザイク・旧ユーゴ” type=”simple”]
7つの国境 … イタリア、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、ギリシャ、アルバニア
6つの共和国 … スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、マケドニア
5つの民族 … スロベニア人、クロアチア人、セルビア人、モンテネグロ人、マケドニア人、
4つの言語 … スロベニア語、クロアチア語、セルビア語、マケドニア語
3つの宗教 …カトリック教、セルビア正教、イスラム教
2つの文字 … ラテン文字、キリル文字
※ 5つの民族とは、5つの主要民族のこと。ほかにも、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア南西部、モンテネグロ西部に多いムスリム人や、セルビア南部のコソボ自治州やマケドニア共和国西部に多いアルバニア人 、そのほかにもハンガリー人、トルコ人、スロバキア人、ルーマニア人、ルシン人、マジャル人、ロマ(ジプシー)などもいました。
また、後記で紹介する『みんな“コスモポリタン”だった70年代のユーゴスラヴィア』でもみられるように、「ユーゴスラビア人」もいました。
民族自認として自身をユーゴスラビア全体に属する者ととらえたり、民族間の混血によって生まれた人や、その地方では少数民族となる人なども「ユーゴスラビア人」を自認したといいます。
[/box]
第二次世界大戦によって荒廃した国土の再建とともに、
こうした 多民族複合国家を1つの国家 として、優れた統率力で ヨシップ・ブロズ・チトー大統領 がまとめていくのでした。

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の大統領、ヨシップ・ブロズ・チトー
「人種のモザイク」と呼ばれた旧ユーゴ。その旧ユーゴが位置するバルカン半島は、「欧州の火薬庫」とも呼ばれていました。
幾つもの民族が入り混じり、民族対立や宗教対立などが絶えることはなかったそうです。
第一次世界大戦の引き金となったのも、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都、サラエボでした。

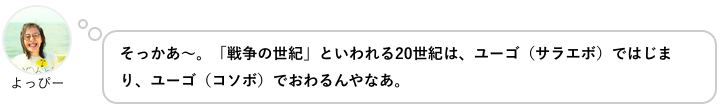
そのような地域で、第二次世界大戦後、6共和国の統合を実現させた終身大統領ヨシップ・ブロズ・チトー。
第二のユーゴは、チトーなしには考えられなかったといわれています。
ちなみに、ヨシップ・ブロズ・チトーの本名は ヨシップ・ブロズ で、チトーは「お前(Ti)があれ(To)をしろ」という口調からついたあだ名だそうです。
チトーは、ソ連のスターリンや、ナチスドイツのヒトラーにも屈せず、東側でも西側でもない 非同盟陣営 を確立し、東西両陣営問わず様々な国と良好な関係を構築していったのでした。
チトーの葬儀には、世界142カ国の政府代表が出席。かつてない規模の国葬に、チトーのカリスマ性があらわれています。
内政においても、 差別主義や民族主義を嫌ったチトー は、民族問題に注力し、各民族・地域間の融和とバランスを巧みにとり、連邦制の維持につとめます。
当時のソ連型社会主義を見直し、そもそも社会主義とはなにかという根本的問題を改めて検討し、「工場を労働者へ」というスローガンを生みだしました。
対ソ連の観点から、労働者自主管理 という新たな社会主義を実現したのです。各共和国(スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、北マケドニアと、ヴォイヴォディナ自治州、コソボ自治州)の 自治権 を特徴とするユーゴ独自の経済政策である 自主管理社会主義 の建設です(後述)。
こうして第二のユーゴは、 非同盟政策と自主管理を二本柱とする独自の社会主義国 と呼ばれました。
[box class=”blue_box” title=”ポイント” type=”simple”]
第二のユーゴは、
- 非同盟政策
- 自主管理
[/box]
ユーゴスラビアはひとつであり、民族主義的な思想を許さない「友愛と団結」を理念に掲げていたチトーの民族政策。
けれどもそれは、民族意識の高い民族主義者にとっては、おもしろくない、腹の立つ抑圧でしかありませんでした。
(チトーの悪口や政権批判等、言論の自由は認められていたが、「アイツはオレたちとは違う民族、宗教だから排除しよう」という民族主義による排外思想家は、秘密警察による監視・摘発の対象になった。)
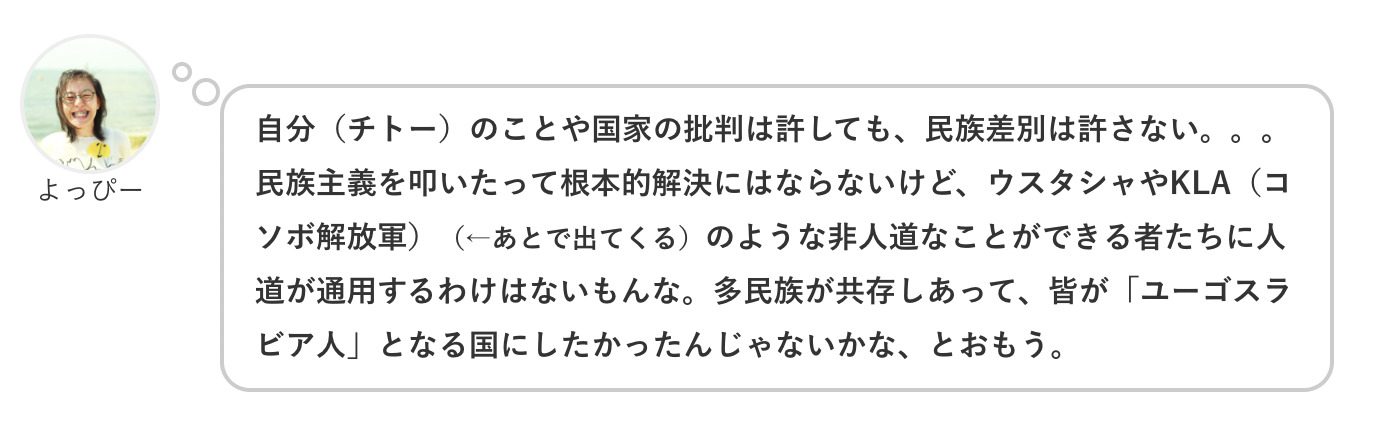
チトー亡き後は、セルビア共和国のスロボダン・ミロシェヴィッチ や、クロアチア共和国のフラニョ・トゥジマン に代表されるような 民族主義者が政権を握りはじめました。
折しも時代は、ベルリンの壁崩壊にはじまる米ソ冷戦の終結です。
冷戦が終結すれば、最前線国家として人工的にひとまとめになっていたユーゴは、団結して一緒に連邦を形成しておく必要はなくなります。共和国ごとに分離独立したユーゴの解体は、自然な流れだったのでしょう。
(旧ユーゴは非同盟主義をとっていたので、各共和国(6つの共和国と2つの自治州)が団結していないとアメリカやソ連に攻撃され、どちらかの陣営に組みこまれてしまう危険性があった。)
冷戦終結後、ソ連が崩壊した1991年。旧ユーゴでは、冷戦時代の緊張がなくなったことで、抑えつづけられていた民族主義が息を吹き返し、民族対立による凄惨な内戦がはじまってしまうのでした。
(よっぴー … 抑えつづけられていた感情や欲求が、冷戦時代の緊張がなくなったことで民族主義が息を吹き返すのは理解できるけど、だからと言って、どうして民族対立による凄惨な内戦をはじめたのか? このテーマは後編で書いています。)
みんな“コスモポリタン”だった70年代のユーゴスラヴィア
以下、サラエヴォ冬季オリンピックの公式テーマ曲を手がけたヤドランカさんへのインタビューから、一部抜粋です。1970年代当時の様子がうかがえます。
「ユーゴスラヴィアは自由で、同じ社会主義の国でもチェコやハンガリーやポーランドとは違いました。チャウシェスクがいたルーマニアのような独裁国家とも全然違ったし、ソ連とも一線をひいていました。ユーゴスラヴィアのパスポートを持っていればどの国もビザなしで行けたし、チェコとかポーランドの人たちは本当にうらやましいと感じていたみたい」
もちろん社会主義に対する不満を口にする人もいたが、人々の間で爆発するような感情には至らなかった。窮屈な統制がなく、教育も医療も無償で、仕事をすればきちんと休みが保障されるという社会では、みんながのびのびと暮らしていた。1970年代のユーゴスラヴィアでは“平等”が行き渡っていたのだ。「近所にはクロアチア人もセルビア人もイタリア人もユダヤ人もいて、みんなお隣同士。お互いの家に出たり入ったりしながら、“この家はちょっと違っておもしろい”みたいな感じでした。いろんな人がいるということが当たり前。黒人の留学生を見ても、ベトナム戦争のときにはベトナムから来た人を見ても、“外国人だ”っていう意識は全然なかったです。言葉が通じればもう友だち。私のジェネレーションはみんな普通にそう思っていました。みんな“コスモポリタン”。すばらしい環境でしたよ」
ユーゴスラビア連邦の崩壊(構成国の独立)
人民が主人公の自主管理社会主義 は、1974年に行われた4度目の改正により、徹底した自由化・分権化が実施されます(74年憲法体制)。
74年憲法体制では、ユーゴ連邦の権限は極めて限られ、6つの共和国と2つの自治州は平等な立場 におかれました。8つの地域は、それぞれに裁判権や警察権、教育権を有するのみならず、完全な経済主権をも有します。
しかしこの「緩い連邦制」は、1980年にチトーが亡くなるや 南北間の経済格差を拡大 させます。カリスマのいないユーゴ連邦では “統合の絆” を維持することはできず、共和国間の対立が激化する のでした。
経済が悪化の一途をたどるなか、80年代に入ると、 ユーゴの経済危機 は一気に表面化します。
1981年には、セルビア共和国に属する、アルバニア人が85%以上を占めるコソボ自治州で、経済的不満から自治権拡大を求める大規模なアルバニア人の暴動が発生しました(この暴動はコソボ紛争のきっかけとなり、ユーゴ連邦解体の引き金の一つともなった)。
セルビア共和国やモンテネグロ共和国など 経済的に貧しい共和国は、ユーゴ連邦による共和国間の経済的格差を解消するための経済政策を求めて、連邦制の強化を求めます。
それに対し、経済的に豊かな スロベニア共和国、クロアチア共和国は、連邦制の解体を要求します。
このように南北間の経済格差が、ユーゴ連邦に対する 要求の対立 となってあらわれます。
[box class=”blue_box” title=”ポイント” type=”simple”]
経済的な成長が遅れている共和国は「社会主義でないこと」に対して不満がつのった。
経済的に発展している共和国は「社会主義であること」に対して不満がつのった。[/box]
こうした情勢を背景として、ユーゴ連邦の中心政府であるセルビア共和国に登場するのが、 セルビア民族主義 を掲げた スロボダン・ミロシェヴィッチ でした。
ミロシェヴィッチは、鬱積していたセルビア人の心理を巧みにとらえて台頭し、セルビア人の 民族主義 をこれまでになく高め、熱狂的な支持を得ていきます。
対してクロアチアでは、ミロシェヴィッチがこれまでの連邦方針を一変させ、連邦権限を強化していくことに反発した フラニョ・トゥジマン が クロアチア民族主義 を掲げて台頭しました。
1989年秋から冬にかけて東欧の共産主義政権が一掃されると(東欧革命)、ユーゴも一党支配を断念し、1990年に初めて、複数政党制のもと 自由選挙が実施 されるのでした。
結果、各共和国ではいずれも民族政党が勝利 します。
それにともなって、統一国家であったユーゴ連邦国の各共和国は、独立を勝ち取ろうとしました。
独立にあたっての利害対立はユーゴスラビア紛争(以下、ユーゴ紛争)を引き起こし、容易に民族対立へと転化します。
戦闘、略奪、虐殺、強姦などが日常的に繰り返された クロアチア紛争 や ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、コソボ紛争 など、第二次世界大戦後では最悪の内戦へと発展して、想像を絶する悲惨な戦いが行われていくのでした。
ユーゴスラビア紛争へ〜ウスタシャとクロアチア独立国
ユーゴ紛争を引き起こしたいきさつは、ここまで述べてきたようなものでしたが、近年におけるそもそものきっかけ(というか、火種)は、クロアチア共和国における民族主義的な政権の誕生 でした。
どういうことかというと、、、
話は、第二次世界大戦、1941年4月に戻ります(『ユーゴスラビア王国』だった「第一のユーゴ」が死んだとき)。
アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツは、ソビエト連邦との本格的な戦争を始める前に、後背地にあたるバルカン半島の支配を固める必要がありました。
ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアが相次いで 日独伊三国軍事同盟 に加わり、残るはユーゴスラビア王国。
ユーゴスラビア王国の摂政パヴレは、ギリシャ以外の国境を枢軸国の勢力に包囲されたことで武力制圧を危惧し、三国軍事同盟に加わり、枢軸国に協力すると決めました(国王と政府はただちにイギリスに亡命)(戦後、王国は滅亡し社会主義国として「第二のユーゴ」が成立する)。
ユーゴ(当時のユーゴスラビア王国)は、ナチスドイツに瞬く間に占領されます。
すると、セルビア人を民族の怨敵とみなしていた、アンテ・パヴェリッチ 率いる ウスタシャ(クロアチア民族主義団体。ファシスト集団)が、ナチスに協力を申し出て、即座に 傀儡国家「クロアチア独立国」の建国 をナチスドイツに承認させました。
独ソ戦に向けて兵士を残しておきたいヒトラーにとっても好都合。この地域の治安と統治を、テロ組織であるウスタシャに委ねたのでした。

↑↓ 上の赤色の部分が、傀儡国家クロアチア独立国。下の画像、現在のクロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナのおおよその領域にまたがって成立させた。

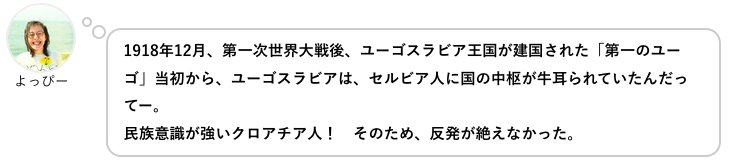
ナチスの傀儡政権を誕生させたウスタシャ。
上の「分割されたユーゴスラビア」画像の赤色の部分には、クロアチア人のほかに、セルビア人も暮らしていましたが、クロアチア人による独立国民国家の樹立を目指したウスタシャは、セルビア人(や共産主義者、ユダヤ人、ロマ族など)を完全排除するため、容赦のない殺戮を繰り返します。その死者総数は、70万人とも100万人とも言われています(正確な人数ははっきりしていない)。
クロアチア独立国国内に強制収容所を建設し、なかでも ヤセノヴァツ収容所 は、恐ろしく残忍な絶滅・強制収容所といわれます。
ウスタシャのあまりの残虐さには、同じく残虐行為を専門としたナチスの保安警察(SiPo)や、特別行動部隊(アインザッツグルッペン)でさえ慄くほどだったといいます。
ヤセノヴァツ収容所
アウシュヴィッツを知らない者はいないが,ヤセノヴァツを知る者は少ない。
>>> クロアチア独立国家 – 慶應義塾大学学術情報リポジトリ より
この論文では、掃討作戦で被害にあったドラクセニッチ村の虐殺や、ダラディナ村のことも書かれています。
また、1991年にユーゴ連邦から独立したクロアチア共和国が、ヤセノヴァツ収容所は、クロアチア民族とカトリック教会を加害者に仕立て上げる、セルビア人の作った「神話」であると公式見解を打ち立てたことや、クロアチア軍が、ヤセノヴァツ博物館で、歴史的資料のかなりの部分を破壊したことなども書かれています。
参考書籍はこちら >>> 『大量虐殺の社会史―戦慄の20世紀』 松村高夫・矢野久著
[amazonjs asin=”4623045382″ locale=”JP” title=”大量虐殺の社会史―戦慄の20世紀 (MINERVA西洋史ライブラリー)”]
ユーゴスラビア紛争へ 〜「チェトニック」と「パルチザン」
ユーゴスラビア王国政府が亡命したあと、ユーゴスラビア王国軍で主流だったセルビア将兵を中心としたナチスドイツ抵抗組織「チェトニック」が結成され、ドイツ軍に対抗しました。
けれども内部腐敗に染まり、規律にも欠けていたチェトニックは、本来の敵たる枢軸軍とは戦おうとせず、クロアチア人とムスリム人(ボスニア・ヘルツェゴビナに住む民族)を残忍な手口で虐殺していきます(クロアチア人がセルビア人を、セルビア人がクロアチア人を…。この殺し合いの連鎖が、のちのユーゴ紛争をより悲惨なものにした)。
代わってドイツに対して抵抗運動をリードし、この内戦を終結させたのが、ヨシップ・ブロズ・チトーの率いる「パルチザン」(人民解放軍)でした。
パルチザンはドイツ軍に対して粘り強く抵抗し、ソ連軍の力を東欧の国で唯一借りず、ユーゴスラビアの自力での解放を成し遂げました。
ユーゴの土地の所有権配分を検討していたソ連とイギリス。チトーは「ユーゴスラビアは100%ユーゴスラビア人のためのものだ」と言い、英国首相チャーチルは逃げ帰ってしまったそう。
ユーゴスラビア紛争へ〜クロアチア人とセルビア人の平等
傀儡国家・クロアチア独立国が崩壊した大戦後の1945年、第二のユーゴで宣言された「4つの平等」のなかで、このふたつの民族が殺戮を繰り返さないよう、「クロアチア人とセルビア人の平等」が明記されています。
[box class=”yellow_box” title=”4つの平等”]
- ユーゴに居住するすべての市民は民族や宗教を越えて平等であること
- ユーゴ共産党や連邦による制限つきではあるが、「主権」をもつ6共和国の平等
- すべての民族・少数民族の平等
- パルチザン戦争への貢献の点ですべての民族、とくにクロアチア人とセルビア人との平等
[/box]
[amazonjs asin=”4004304458″ locale=”JP” title=”ユーゴスラヴィア現代史 (岩波新書)”]
この4番目の「クロアチア人とセルビア人との平等」が記されていたことから、クロアチア共和国の憲法にも、 共和国は「クロアチア人とセルビア人の国家」である と明記されていました。
ところが1990年5月の選挙で誕生した 民族主義的な「クロアチア民主同盟」の政権は、 憲法を改正 し、これまで「クロアチア人とセルビア人の国家」とされていたものを、「クロアチア人の民族国家」に改めてしまいます。
これに対しクロアチア共和国内のセルビア人は反発し、武装して対抗します。
ちなみに、ユーゴが解体される1991年までの、6つの共和国と2つの自治州に住んでいた主な民族は、以下のようになっていました。↓↓↓
[box class=”yellow_box” title=”ユーゴスラビアを構成する6共和国と2自治州に住む、主な民族”]
● クロアチア … クロアチア人、セルビア人
● ボスニア・ヘルツェゴビナ … ムスリム人、セルビア人、クロアチア人
● セルビア … セルビア人、アルバニア人、マジャル人、ムスリム人
● モンテネグロ … モンテネグロ人、ムスリム人、セルビア人、クロアチア人
● マケドニア … マケドニア人、アルバニア人
■ コソボ … アルバニア人、セルビア人、トルコ人、ムスリム人、モンテネグロ人
■ ヴォイヴォディナ … セルビア人、マジャル人、スロバキア人、ルーマニア人、ルシン人、クロアチア人
出典:Wikipedia – ユーゴスラビア社会主義連邦共和国
[/box]

民族浄化がもたらすユーゴスラビア紛争
ユーゴ紛争は、ユーゴ連邦国の解体の過程で起こった内戦です。
独立にともなった紛争は終結までに数多くの犠牲者を出しながら、1991年から2001年まで、10年にわたって続きます。
[box class=”yellow_box” title=”ユーゴスラビア紛争”]
- スロベニア紛争(十日間戦争)(1991年)
- クロアチア紛争(1991年 – 1995年)
- ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争(ボスニア紛争)(1992年 – 1995年)
- コソボ紛争(1996年 – 1999年)
- マケドニア紛争(2001年)
[/box]
はじまりは 十日間戦争 と呼ばれるスロベニアでの紛争で、その後、主要な紛争が勃発しました。
民族の混在が少なかった スロベニアやマケドニアが比較的スムーズに独立を達成した一方で、
民族の混在が多かった クロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボでは、 民族浄化 のもと悲惨な戦いが行われていくのでした。
ユーゴスラビアの狂気は、わたしから見ると、3つあります。そのひとつが、この「民族浄化」です。
民族浄化の狂気については、後編につづきます。


