 こんにちは、
こんにちは、
AI-am(アイアム)の
よっぴーです。
子どもが自己肯定感を育むにはどうしたらよいのか?
どう育てたら「学び」を楽しむ子どものまま、健やかに成長していくのか?
親の役割とははなにか? その後編です。
もくじ
家庭は学校ではない
親の仕事は子どもを愛すること のつづき、後編です。
「これはひまわりじゃないよ、チューリップだよ」と教えても、チューリップの花をひまわりと言うAちゃんに、親は怒りを覚えていきます。
それはまるで「1+1=2」になることをいくら教えても、間違った答えを言う児童に対して、「なんでこんな簡単な問題がわからないんだ!」と怒鳴りだす先生のようです。
でも、家庭は学校ではありません。
それなのにどうして、お家でも学校みたいに「そっちじゃないよ! こっちだよ!」と言ってしまうんでしょう?
親にまで言われつづけたら、子どもはどうなっちゃうんでしょう?
子どもが自己肯定感を育むには、どうしたらよいのでしょうか?
大人には、正しく覚えなくてはいけない、間違えてはいけないという意識が強くあります。
だから、自分はもとより子どもにまで、間違いを指摘してしまう。
「失敗してもいい」という大人のうそ
その意識は、わたしたち自身の子ども時代から根づいてきたものです。
「何回言ったらわかるの! それはチューリップじゃないって言ってるでしょ! それはひまわりです」
「もうすぐ小学生なんだよ、みーーんなもうひらがなを書けるんだよ。さあ、練習してみましょう」
「どうしてできないの、そんな簡単なこと! 困るのはあなたでしょ」
etc……
こんなふうに言われつづけてきたわたしたち。しかも、 間違ったら怒られる んです。
そこで、間違わないようにしようとおもって尋ねると、今度はこう言われるんです。「 前にも言ったよね? 」(← こういうの、職場でもありますね)。
「失敗してもいいんだよ」とおとなは言うけれど、その同じ口が、「走ったら転ぶよ!」と言うんです。「早く寝ないと朝起きれないよ!」とけしかけてくるんです。
日々、こんな矛盾を浴びせられて、どうして子どもがおとなを尊敬することなど期待できるでしょうか?
「そっちじゃないよ、こっちだよ!」と言われつづけた子どもはどうなるのか?
まったりとした午後の電車内で見かけたこと。
遠足にでも行ってきたのか、たくさんの子どもたちが電車に乗ってきたんですね。
席には座ったらいけないようで、でも、ひとりの男の子が座りました。
その途端、
「わるーーー!!」
「ずるーーー!!」
「立っとかなあかんねんでぇーーー!」
「先生に怒られんでぇーーー!」
「先せ~い! ○○くんが座ってますー!」
ちなみにこの子たちは幼稚園児。
案の定(?)、先生は注意しました。「○○君、先生の言うことを聞けない子は次の駅で降りてもらいますよ!!」
おいおい。
教育に銃(脅し、罰)は要りません 。
「そっちじゃないよ! こっちだよ!」と言われつづけた子どもはどうなるのか?
そりゃあ、こうなりますよね。わたしたちと同じようなおとなになりますね。
正解が大好きなおとなになって、今度は「そっちじゃないよ! こっちだよ!」を連呼する側になっていく。
延々と繰り返される「支配と服従」の関係……。
ただ在ること(Being)
目の前にいるわが子のことを、「言うことを聞かない子」とか、「思い通りに育たない困った子」におもえるときっていうのは、親の価値観や好みに従わせようとしているとき だと思うんです。
だから、しんどい。
「正解」を先に用意すると、子育てはしんどくなってしまいます(子育てに限らず、決まった答えのないはずのものに決まった正解やゴールを先に置くと、生きることそのものが窮屈になる)。
子どもが学校に行かなくなって(行けなくなって)親が悩むのも、「正解」を求めるから。子どもに正常であって欲しいと望むから、苦しい。
エライ人や社会は、すること(Doing)を強迫しつづけるけれど、
ただ在ること(Being)、人間の尊厳というものを照らしていきませんか?
そのことに気づいたら、学校に行くことが正常で、行かないことは正常ではない、なんて括りを外していくことができます。
スーパーの帰り道。道ばたに咲いているチューリップを指さして、もうすぐ3歳になるAちゃんが「ああ、ひまわりー」と言ったとします。
こんなとき、「これはひまわりじゃないよ、チューリップだよ」と教えられるんじゃなくて、
「ああ、ひまわりー」って言ったとき、「あーほんとだー。咲いてるねぇ〜。きれいだねー」って共感してもらえたら、ただただ嬉しいなあとおもうのです。
わたし(親)もまた、「いつのまに「ひまわり」を覚えたんだろう? どこで覚えたんだろう? わあ〜成長してるんだなあ」と、心のなかがよろこびに満ちます。
怒ってもいいんだよ、泣いてもいいんだよ
常識や固定概念がゆるんでいくと、これまで否認していたダメな自分をも、ただそのまんま受け入れられるようになって、自分を肯定できるようになってきます。
にんげんだから、子どもと <いま ここ> に在って、イライラ・イーーーーー!! ってなったときは、ぶるぶる体操でもしながら文句言いあって、互いに泣いて、笑おう!
誰にだって凸凹はあるのだから。それが自然。
↓↓ ぶるぶる体操
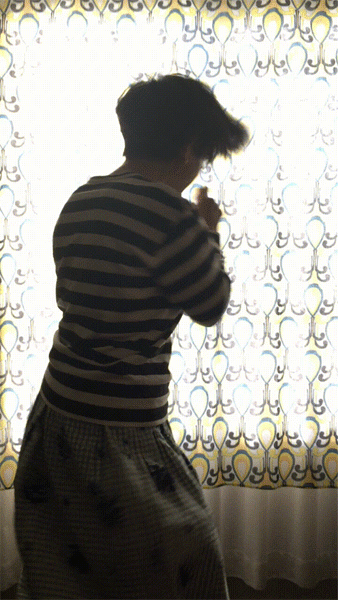
↑↑ ぶるぶる体操を外ででもできるようになったら、もうそれ、自己肯定感ばっちぐー。
神様はなにも禁止していない
親が自身を肯定できたら、子どももまた自分(子ども本人)を肯定していられます。
走ったらこけて…… 「だから言ったでしょ! ママの言うこときかないからよ!」とかとか言われるんではなく、「だいじょうぶ?」とぬくもりをくれる親。
早く寝なかったから起きるのが辛い朝も…… 「さっさと寝ないからでしょ! 自業自得よ、あなたが悪い!」などと朝からヒステリックにジャッジされるのではなくて、「眠いね〜」と <いま ここ> にいてくれる親。
「失敗してもいいんだよ」に嘘や矛盾がなければ、こころは健全に育って、子どもは(親も!)恐れず、堂々と「暮らし」をしていくことができます。
感情とともに、表現の自由も許されているのなら、ありのままの自分と向き合って、自分の学びに没頭していきます。
評価のない環境は、好奇心を殺しません。
すること(Doing)ではなく、あること(Being)
幼い子どもにとっての社会とは、家庭です。家庭が、その子にとってのすべての世界。
だから、だから! 親の役割は、子どもを愛すること。
「あなたは、あなたのままで、かけがえのない存在だ」ということを、矛盾のないメッセージで実感させることです。
子どもが大きくったってだいじょうぶだよ。その子の「好き」なことをちょっと一緒にしてみよ。
一緒にアンパンマン見るとか、ゲームするとか、パンケーキ食べに行くとか、たあいもないおしゃべりするとか……。
なんだっていいです。重要なのは、すること(Doing)ではなく、ただ あること(Being)!
親のほんのちょっとの「変化」で、子どもは、「学び」を楽しむ子どものまま、健やかに成長していきます。


