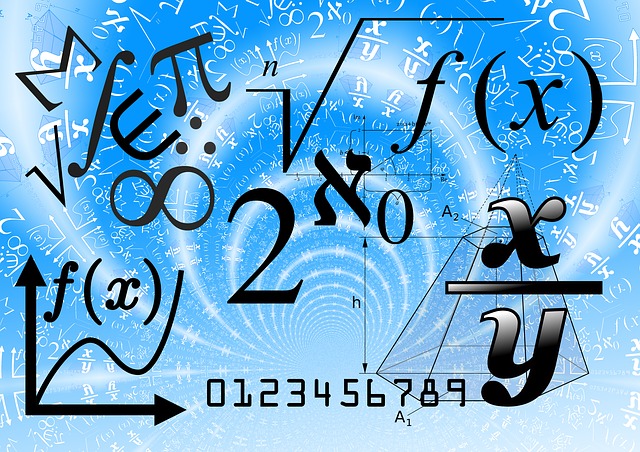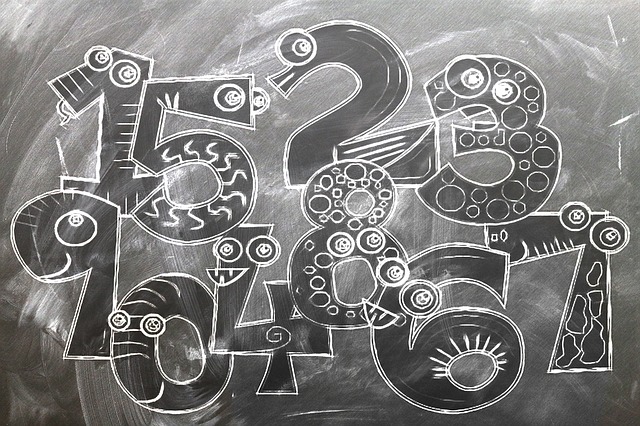こんにちは、
こんにちは、
AI-amの
よっぴー です。
小学校、中学校、および高校も魅力を感じなかったため通わず(学校側からみれば不登校)、高卒認定から大学受験に挑んだ娘、星山まりんさんの話。数学篇です。
中高で習う数学は12時間で習得しました
魅力をかんじなかった小中高には行かなかったのですが、大学には魅力をかんじた? 17歳(学年でいえば高3)の夏、突如、大学に行こうと思い立ったまりんさん。
小学校から行っていなくても、大学に行くことはできます。
この場合、高校を出ていないので、かわりに、高等学校卒業程度認定(旧大検)の資格を取得します(以下、高認)。そうすると高校卒業者とおなじように、大学を受験できます。
この高認試験合格に必要な8教科を2ヵ月半でマスターしたことは、 12年間の勉強が2ヵ月半?〜小中高には行かないで大学に行った娘の話.高認篇 で。
6年間かけて学ぶはずの算数は、じつは、たった20時間で! わずか3日で! クリアできるものだったことは 6年かけて学ぶはずの算数は3日でクリアできる!〜小中高には行かないで大学に行った娘の話.算数篇 で綴ったのですが、
なんと! 数学にいたっては 12時間でした。
数学だけは、数学の先生についてもらいました。週1回、1回につき1時間。それが12回です。
中学、高校の6年間、52560時間のうち
中学、高校の6年間、52560時間のうち、いったい「数学」にどれぐらいの時間をつかうのでしょう?
わたしは、高校生当時、2年生から理系にすすんだため、時間割に数Ⅱや数Ⅲなどが1日3時間(3コマ)とかあった記憶があります。
イヤでイヤでたまらなかった授業は、あまりに退屈で、それこそが時間の無駄づかいでした。
しかも大学は文系に行ったので、受験に数学は必要なかったですし(。>﹏<。)
数学の予習、復習の方法
受験にむけての勉強を始めてからもバイトはしていて(高認やセンター試験の前日もしごとでした)、週に1回、バイトが終わったあと塾に行く。
マンツーマンでの授業を終えると、カフェに入って、いま教わったばかりのところを、1時間みっちりと復習をする。
バイト先も塾も都心だったので、仕事や勉強に最適なカフェは多数あります。
家に帰ってからするよりも、外での勉強のほうが集中できたそうです。電源やwifiも完備されていますしね。
高認に受かるためだけの数学なので、高得点でなくていいんです。
高認は、落とすための競争試験ではないので、合格定員(合格者数)の上限はありません。
学力の意味は「学ぶ力」
6年間で習う算数を、20時間、3日で習得したっていうだけでおどろきなのに、数学にいたっては12時間。
教えてもらっていた先生はプロフェッショナルで、教え方が非常に秀でていたからですが、それでもやっぱり言葉を失います。
7+8=? この足し算がわからなかった人が、30時間後には、0°≦θ≦180°とする。tanθ=-√3を満たすθの値を求めなさい を解いているんですよ。
学力とは字のごとく学ぶ力のこと。学ぶ力は生まれてから最期までだれもがもっているものです。
あいかわらず学力低下が叫ばれていますが、大人の側の「与えよう」、「身につけさせよう」とするものと、子どもが今「得たいもの」、「求めているもの」とにズレがあるだけです。
学力なんてものは計れるものではありません。個性や個人差を無視した、1年生の一学期には◯◯を、2年生の二学期では△△、と要求されている「学習指導要領」に縛られていませんか?
人生では、必要な時期に、必要な人としかつながらないように、人は自分にとって必要な学びとしかつながりません。
だれもが「学生」なのに、どうして小中高の12年間だけは「生徒」呼ばわりするんでしょうね。