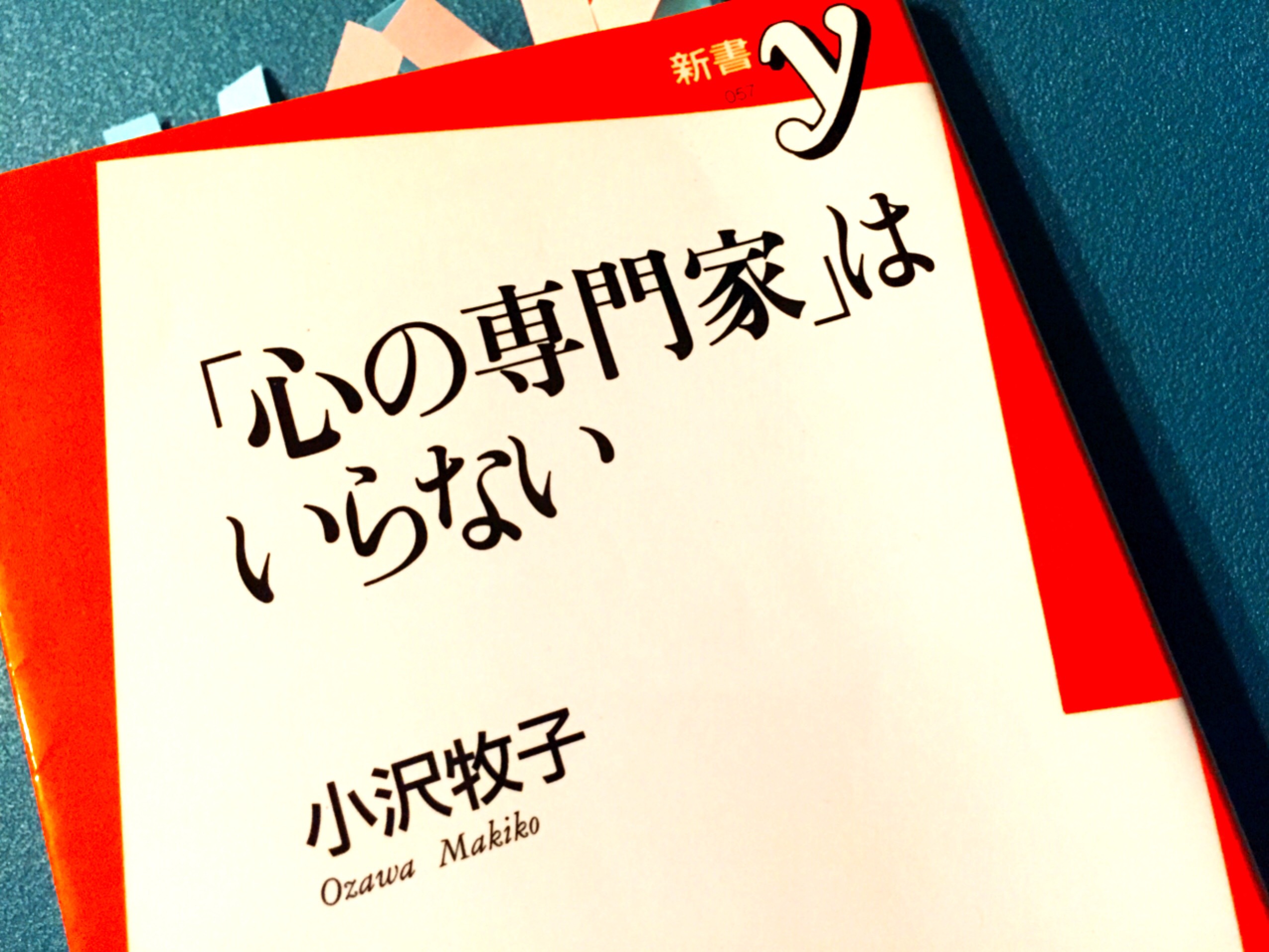こんにちは、
こんにちは、
AI-am(アイアム)の
よっぴーです。
小沢牧子著『「心の専門家」はいらない』(洋泉社/2002年)という本があります。
「心の専門家」(臨床心理士やカウンセラー)の氾濫と、それを喧伝するマスコミ、そしてそれに浸食されていく世の中への強い気がかりから書かれた本で、臨床心理学の何が問題かを根底から問われています。
不登校だったり、行き渋っていたりするわが子のことで、学校のスクールカウンセラーさんにご相談される親さんや、
学校に行きたくないとか、担任がイヤとか、別室登校等をしているとかで、スクールカウンセラーさんに話をきいてもらいたいご本人さんは、
『 学校に行きたくないなら休んでよいという法律「教育機会確保法」は不登校してる子どもたちを応援する 』同様、
カウンセリングのカラクリを知っておいたら心の準備になるかも?! です。
※ この記事は、スクールカウンセラーさんを否定しているものではありません。
ちゃんと存在できる大人
小沢牧子著『「心の専門家」はいらない 』の第三章「スクールカウンセリングのゆくえ」に書かれている「問われるおとなのかかわり」のなかに、以下の文章があります。
※ 赤色の下線はわたしが付けたものです。
カウセリング依存が進行するのは、年長世代が自分たちの生き方を見せたり何気なく語ったりしていないことともかかわりがあるのだ。「心の問題」というのは、心理学的知見や技法のことではなく、現実にはしょせん生き方の問題のことである。日常の関係のなかで年長世代のさまざまな生き方や考え方に接する機会こそ、求められているのだと思う。「高い山」から眺める「プロ」よりも「低い丘」にいる「セミプロ」のほうが、子どもや若者の望む姿であることは確かであろう。しかしより強く求められているのは、平地で対等に向き合う姿勢を持ったおとなたちであるのだと思う。
引用:小沢牧子著『「心の専門家」はいらない 』
でもって、
先日 まりん さんが投稿した『 思春期の子どもの心を理解したいときに観る映画4選(邦画編)』の記事。
4選のうちのひとつ、『 青い春 』についての文の一部に以下があった。
※ 赤色の下線はわたしが付けたものです。
映画には大人がほとんど登場しないけれども、彼らの世界から除外されない大人がふたりだけいる。
ひとりは教師の花田先生(マメ山田)、ひとりは購買部のおばちゃん(小泉今日子)。
いちばんイノセントな彼らの世界のなかでちゃんと存在できる大人って、こういうことだ。
まりんさんのこの記事を読んだとき、小沢牧子さんの『「心の専門家」はいらない 』の上述の部分をおもいだしました。
本書のいう「心の専門家」とは、臨床心理士 や カウンセラーと呼ばれる方々のことで、
臨床心理学、カウンセリングを通して行われている、社会の心理学化と、心のモノ化に、警鐘を鳴らす本だと思うのです。
デモクラティックスクール育ちのまりんさんは、他の デモクラティックスクール・サドベリースクール 育ちの子どもたち同様、
子ども世界のなかで ちゃんと存在できる大人(先生)と学校生活をおくってきた人です。
平地で対等に向き合う姿勢を持ったおとなたち とはどんななのかを肌で知っています。
だから、ほんものか、にせものか、(対等を装った権力者か、権力に依存している大人か、ちゃんと存在できる大人か)、一瞬で見抜く。
『 青い春 』を観て、「イノセントな彼らの世界から除外されない大人」にもいちはやく目がいくのはそこんとこなんだろう。
ところが一般の学校(公の学校)には、平地で対等に向き合う姿勢を持ったおとなたち は滅多にいません(こういったタイプの大人の方は、その多くが教師やカウンセラーを辞められる)。家庭でもおなじです。
多くの子どもは、平地で対等に向き合う姿勢を持ったおとなたち を肌で知ることなく、大人になっていきます。
だから、学校依存、権力依存の大人が、こんなにも多くなる。だから、優しい人にたよってしまう。
こうして、ただ単に学校「が」合わないだけの人なのに、学校「に」適応しない「問題の子どもたち」(実際はなんの問題もない子どもたち & 親)扱いにされた人たちは、
対等を装った権力関係のもと、「プロ」の方や、「セミプロ」の方たちの親切に囲いこまれて、
傾聴・共感・支持・自己実現といったカウンセリング技法の、優しく巧妙な言語戦略によって、問題をすりかえられていきます。
問題をすりかえる
「登校拒否」研究が注目を集めた1960年代初頭から登校拒否研究班に加わるなど、臨床心理学に携わってこられた小沢牧子さんは、本書で、
臨床心理学は、現代社会で人気を集め、良きもの必要なものと信奉されているが、
カウンセリングとは、社会適応を促すための方法であり、
やさしく巧妙な管理技法であり、
問題をすりかえる技法である と述べられています。
対等関係を装い、「社会や制度の問題を、個人の心の問題へすりかえるカウンセリング技法」と、「社会に合わせるように、個人を変えようとする思想の欺瞞性」。
これらの危険性を、何度も、何度も、本書のなかで繰り返されるのです。
社会や制度、生活の問題を、個人の心の問題へすりかえる、この「ずらし」は、カウンセラーが意図的に行っているのではなく、
傾聴・共感・支持・自己実現などといったカウンセリング技法そのもののなかに、この機能が構造的に組み込まれているといいます。
本には「ずらし」のカラクリ(機能)がどのように組み込まれているのか、詳しく書かれてあるのですが、たとえば、こんなの ↓↓
たとえば、クライエントがカウンセラーにこう訊ねたとする。「先生はお子さんがいらっしゃるのですか?」。その場合さまざまな返答がありうるだろうが、もっともカウンセリング臭の強い返答は、次のものである。「それが気になりますか?」。
引用:小沢牧子著『「心の専門家」はいらない 』
話された内容や事柄ではなく、話している当人の感情に焦点を当てて返し、「子どもがいるのか、どうか、それが気になった自分」に目を向けさせ、自分の内面の問題としてとらえなおすことを促します。
このようにして、「問題」の原因が他のところではなく、自分の内部に属しているのだとどれだけ自覚させられるかで、カウンセリングの成功度が計られていくのだそうです。
ふつうにおしゃべりしませんか?
私事でありますが、
不登校をしていた息子 の中学校のスクールカウンセラーの方から「是非一度、お母さんとお会いしてお話したい」と連絡があり、わが家に来られたときのことです。
スクールカウンセラーの方が言います。
「学校に行かないで将来はどのようにお考えですか? このままでは何にもなれないじゃないですか」
>>> そのときのことを書いている記事
「学校に行かないで将来はどのようにお考えですか?」とカウンセラーの先生に尋ねられて
で、↑↑ の記事に書いたように答えたとき、スクールカウンセラーの方は、「そう思い込もうと頑張られていらっしゃるのですね」と返されたのでした。
だもんで、言いました。「せんせい〜、ふつうにおしゃべりしましょうよ」と。
スクールカウンセラーさんとしゃべっていて、
- 「??? なんかへん」とか、
- 「なんかいいふくめられてる?」
- 「心にもない いい子ぶりっ子の返事してもた?」
てなかんじを受けたときは、
「ふつうにしゃべろ〜よ」、これどうでしょうか。
カウンセリング技法が、制度として教育や産業などの現場に組み込まれているけれど、問題を、個人のことにすりかえられないでね。
カウンセラーが自分の考えを語らないだけにいっそう、クライエントは「いい子」としての答えを出す方向に自発的に傾いていくのだと思う。いわゆる、自発的適応である。巧妙な装置であると言わざるをえない。
(略)
個人としての生き方を見せず自分の考え・価値観をほとんど語らないが、無言の権威は体制的価値を代弁し、結果として社会適応を促す作用を持つ。生き方が見えている人に「あの人ならどう言うだろうか」と相談に行く場合との違いがそこにある。カウンセリングはこうして、ソフトな社会管理役割を担っている。
引用:小沢牧子著『「心の専門家」はいらない 』
学校にスクールカウンセラーがいるカラクリ
そもそも、
カウンセリングとは、社会適応を促すための方法であり、
やさしく巧妙な管理技法であり、
問題をすりかえる技法である
……って、
不登校は制度の問題なのに、
たかが不登校 なのに、
行きたいのに行けなくて、つらいね、とか…
行けないあなたはかわいそう。助けてあげますね、支援してあげますね。とかなんとか… 、、、
自分の内面の問題にすりかえられているってことじゃないか!
スクールカウンセラーさんは、そうは言わない。
「ああ、それ、あなたがわるいんじゃなくて、学校の制度のほうがおかしいんですよ。学校にこなくっても、な〜んも問題なんてないからね。
卒業はできるし、進学もできるし、就職もできます。 不登校でも進学できる高校 もこんなにたくさんありますよ。
そういったことが書かれている本(たとえば、わたしたち親子が書いた 『小さな天才の育て方・育ち方-小・中・高に通わず大学へ行った話 』とか ^^)もいろいろあるし、
実際に、学校に行かなくても ちょうハッピーに過ごしている人(たとえば、まりん さんも ^^)もたくさんいますよ。
学校にこなくっても、あなたの未来は狭まりません」
と、事実は言えない。
いまは この法律が成立して やっと、フリースクールやホームエデュケーションもあるよ、と言えるようになって、スクールカウンセラーの方の対応もすこし変わったかもしれません。
でも、基本的に、スクールカウンセラーとして雇われている限り、学校の側に向いてない発言はできない。
もちろん、スクールカウンセラーさんとお話をすることで、気持ちが楽な方向へ向かった方もいるとおもいます。
でも、いいカウンセラーさんもいればそうじゃないカウンセラーさんもいる、という話ではなく、この構造の問題に目を向けていきたいですね。
長くなったので、後半、『 心の専門家は必要なのか?スクールカウンセラーが学校に導入された背景とサーカスの動物のようにしつけられるわたしたち 』へつづきます!
[kanren postid=”11921″]
今日の本
「心の専門家」はいらない/小沢 牧子
現在、社会で良きもの、必要とされているものを根底から問う! 「心の専門家」の氾濫と、それを喧伝するマスコミ、それに浸食されていく世の中。ここ五、六年、事件・事故が起こるたびに声高に叫ばれるものに「心のケア」「心の教育」という耳に心地いい言葉がある。なぜ、この風潮はかくも社会に浸透し、蔓延したのか? 日常の関係に目を向けることを避け、「心の専門家」に依存し、そこに救済願望を託す「心主義」と言いたくなる傾向に対し、長年、臨床心理学の問い直いに携わってきた著者が、この学問の何が問題かを白日の下にさらす。
[amazonjs asin=”4896916158″ locale=”JP” title=”「心の専門家」はいらない (新書y)”]