 こんにちは、
こんにちは、
AI-am(アイアム)の
よっぴー (吉田晃子)です。
子どもが親のお金を盗む のってどうすれば盗まなくなるんだろう?
親のお金を盗む子ども のこと、
盗まれる親 のことを書いています。
もくじ
子どもが親のお金を盗む背景
「子どもが親のお金を盗みます。どうすればいいんでしょうか」と、ご相談を受けました。
「どうすればいいのか?」という悩みは「どうすれば盗みをしなくなるのか?」ということだとおもうのですが、
対処の前に、どうして盗むのか? ということを考えたいとおもいます。
子どもは悪いことが悪いことだとわかっている
まずはじめに知ってもらいたいことは、子どもは悪いことが悪いことだと分かっています。
だからこそ、子どもが親のお金を盗むその背景はいろいろだとおもうのです。
① 小学校高学年ぐらいから中学、高校生年齢と、それまでに盗癖のない子どもが、あるときから親のお金を盗むようになった
② 幼児や低学年の年齢の子どもが、特に欲しいものがあるわけではないが親のお金を盗む
この2点だけでも背景は異なります。
子どもが親のお金を盗む理由と心理
前者 ① の場合なら、たとえば以下のようなことが考えられますよね。
- 所有欲(物欲。お菓子、カード、ゲームソフト、ゲームセンター、服や鞄、交際費など)によるもの
- カツアゲ等で誰かに脅されている
後者の ② であれば、
- 兄弟姉妹でおこづかいの額が違う
- 最近、弟、もしくは妹ができた
- お金のことで夫婦がケンカをしたり、他者ともめたりしている
など、
「寂しさ」「悲しみ」「恐怖」といった想いから自分のことを見てほしい、親に気付いてほしいという切実な願いで、愛を盗む=お金を盗む 心理が働いています。
一般的な2つの対処法
「子供・お金・盗む」などのキーワードで検索してみると、たくさんのページが対処法の答えを載せていました。
その答えは、大きく括ると以下の2つの意見に分かれています。
- 親のお金を盗むのは犯罪なのだから、手をあげる、警察に連れていく、など徹底的に叱らなければいけない
- 叱るのは逆効果だからまずは冷静に話をしましょう
親のお金だと捉えてしまっても仕方ない家庭に親がしたんだろう?
そんななか、どこにも載っていなかった(たぶん)意見を、AI-amメンバー まりん さんが言います。
[voice icon=”https://ai-am.net/wp-content/uploads/2019/05/B2CC8D34-FA7A-4100-8229-E28E83D28EDE.jpeg” name=”まりん” type=”l big”]お金が不透明やからやん。
親が「お金」にカギ括弧をつけ、タブー視して、子どもに見せない。
そのお金は、「親の」お金 やとおもってるからやろ?
だから仮に1万円を盗んでも、子ども自身は痛くない。子どもは自分の首を絞めていることに気づかないし、気づけない。
でもそうしたんは親やろ?
親のお金やというふうに捉えてしまっても仕方ない家庭に、親がしたんやろ?
うち(家)みたいに家計もオープンやったら、「お金」に境界線をひいてないから、1万円盗んだら(=1万円なくなったら)家賃が払えなくなることを、子どもも直に知ってた。
家にあるお金を 「親の」お金 とは捉えない。
[/voice]

「問題の子どもというものは決していない。あるのは問題の親ばかりだ」
さらに、どこにも載っていない答えです。
悪いのは決して子どもの方ではないと言い切るのは、 金八先生が担任だったら私は2秒で不登校します の記事でもちらりと触れた、イギリスの教育者、A.S.ニイルです。
ニイルは、「問題の子どもというものは決してない。あるのは問題の親ばかりだ」と言います。
下記は著書『問題の子ども』からの引用です。
小さな子どもに「利己的になってはいけない」というのは間違っている。子どもというのは、みなエゴイストなのだ。子どもにとって世界は自分だけのものである。子どもの願望の力は強い。子どもはひたすら願望を満たそうとする。(略)もしリンゴがあれば、彼の願いはそれを食べることだけだ。もし母親が、そのリンゴを弟と分けて食べなさいといえば、おそらく彼は弟を憎むことになるだろう。博愛主義は、もっと大きくなってから生まれるものだ。博愛主義は、利己主義はよくないと教えたりしなければ、子どもに自然に身につくものなのだ。もし子どもが利己主義を捨てるように教えられれば、博愛主義はおそらく一生身につかないだろう。博愛主義は利己主義の進化したものだ。博愛主義者というのは、他人を喜ばすと同時に自己自身の利己主義を満たす人のことにすぎない。
子どもの利己主義を抑圧する母親は、その利己主義を固着させてしまう。満たされない願望は、無意識の中で生き続ける。利己的であってはいけないと教えられた子どもは、ずっと利己的なままで終わるだろう。
このあと、盗み癖がある7歳の男の子の話が書かれています。
男の子は母親の悪意のない軽いウソによって盗み癖がつく不幸な子どもとなったのですが、ニイルの「正直」な一言で、盗癖は治っていくんですね。自我が満たされて。
自我が満たされると、そこには善と呼ばれるものが現れ、自我が満たされないと犯罪性と呼ばれるものが現れます。
犯罪性と愛とは密接に結びついています。
子どもが求めているのは愛と理解である。善良なままで成長する自由だ。子どもが善良なままで大きくなる自由、これをもっともよく与えることができるのは、本当は親である。しかし世界は困ったことでいっぱいだ。そんな婉曲的な言い方をやめてはっきりいえば、世界は憎しみであふれているといったほうがよい。そして子どもを問題の子どもにするのは、親自身の心の中の憎悪である。それは、犯罪者に罪を犯させるのが社会にしみわたった憎悪であるのと同じだ。救いは愛にある。しかし愛を強制できる人はだれもいない。だからもし世の中に希望があるとすれば、それは寛容を学びとることである。おそらく寛容こそ愛であろう。
寛容を学ぶには、なによりもまず自分自身に問いかけねばならない。「寛容と慈善は家庭で始まる」というが、内省こそは、知恵の始まりとまではいわないとしても、寛容の始まりである。問題の子どもをもつ親は、静かに腰をおろして自問自答しなくてはいけない。
「私は、子どもに寛容を示しただろうか。私は信頼を示しただろうか。理解を示しただろうか。」
私は理論を述べているのではない。私は、問題の子どもが私の学校に入ってきて、幸福な子ども、つまり普通の子どもになっていくのを知っている。私にはよくわかる。この治療のプロセスにおいていちばん大事な要素は、子どもに寛容と信頼と理解を示すことだ。
[amazonjs asin=”4654004718″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”新版 ニイル選集〈1〉問題の子ども”]
「聞く」ではなく「聴く」
親の財布からお金を盗む子どもの対処法は、対処するという考え方ではなくて、対応すること です。
その対応とは、まずは、聴く ことです。
話をするのではなくて、話を聴く。
ただ、この「聴く」が非常にむずかしい。
[aside]お知らせ
「親と子がハッピーになるコミュニケーション講座」がお手軽になりました!
これまで、この記事を読んでくださった方々の受講者さんも多かった「親と子がハッピーになるコミュニケーション講座」が、対面から、動画でマイペースに、何度でも学べるスタイルへと生まれ変わりました。
どう聴けばいいのか? をはじめ、どう言えばいいのか?
文字を読むだけでは実感・実践できない「聞きかた」や「話しかた」、また、どう話し合えばいいのか? の「問題解決法」が、いつでも、どこでも、なんどでも動画で見れます。
>>> 親と子がハッピーになるコミュニケーション講座 の詳細はこちら
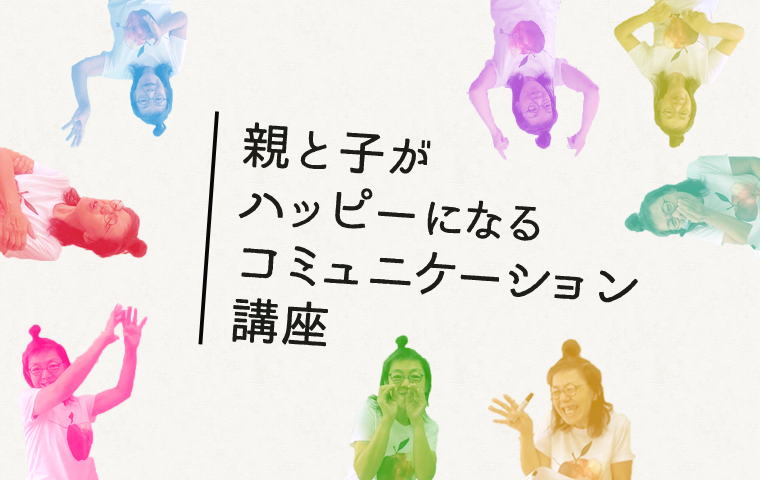
[/aside]
「聴く」ができていなかったから今にいたっているのなら、なぜ、できていないのか。
わたしたち親自身が子ども時代に、「聴いてもらう」「聴いてくれる」が、日々の暮らしのなかに無かったからだとおもいます。
無いものは身に付くはずもなく…。
なにせ親も教師も、大人は、「聴く」の前に、「教える」をしますから。「聞く」ことすらしないで。
でも、だったら、「聴く」をマスターしていけばいいよね。
お金を盗む子ども。。。まずは子どもの心のうちを聴く。そこからかな、とおもいます。
この行為こそが、子どもが求めている愛と理解へと通じるのです。
↓↓↓ 子どもが親のお金を盗むその行為に考えられる3つのケースと共通原因、盗みが治る方法を書いています ↓↓↓
[kanren postid=”5002″]
↓↓↓ 聴くってのはどういうことか? を具体例をだして詳しく書いています ↓↓↓
[kanren postid=”7071″]


