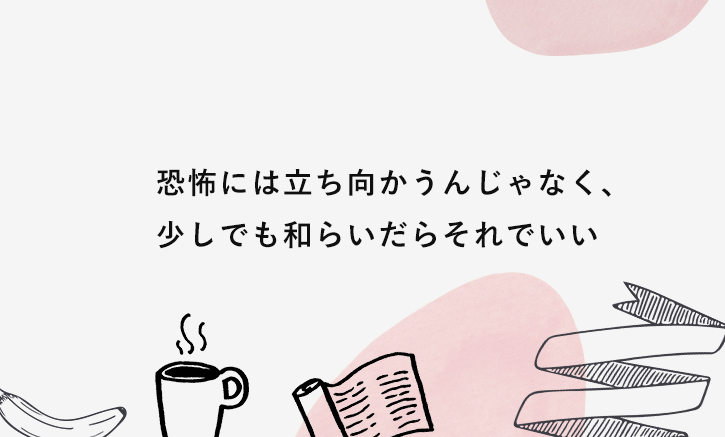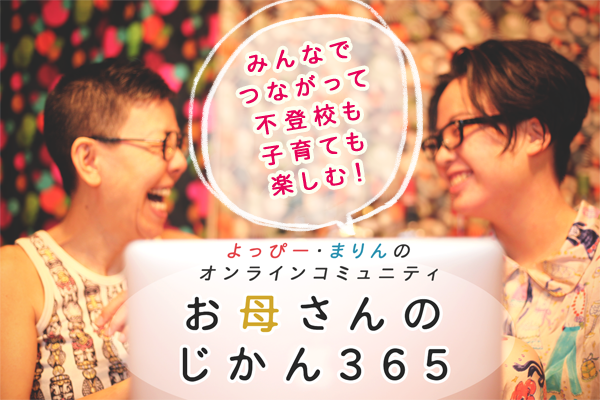こんにちは、AI-am(アイアム)の よっぴー です。
デモクラティックホーム🏡のための新しいおうちが大のお気に入りのわたしたち。でも、庭や畑の虫たちがとにかくこわい! でも、どんどん茂る草木を放置はできない!
そしてよーくわかったんです。恐怖には立ち向かうんじゃなく、恐怖を乗り越えるのでもなく、恐怖は少しでも和らいだらそれでいい。
子どもが不登校をはじめて、「こわい」でいっぱいになっている親や、学校の先生や校長・教頭とお話しするのが「こわい」ときも同じです。3つのステップで恐怖を和らげて、安心アイテムを見つけよう!
もくじ
畑をやりたいわたしたち、草木のそばで生きる虫たち
Facebookでは、イチゴやベリーの実がなって嬉しい! 草花たちの図鑑って便利だねー! などなど投稿しているけれど、うらはら虫がこわい!!
蚊やアリなど害虫と呼ばれる虫たちはむろん、蝶やカエルもこわい!
デモクラティックホーム 🏡 をするにあたり、みんなに来てもらいやすい立地と間取りを重視しただけじゃなく、庭で畑をしたかったもんだから、一目惚れした小田原のおうちはサイコーに気に入っています。
いまも毎日、ことあるごとに「このおうち大好き〜♪」と連呼する。が、虫がこわい!!(六本木ヒルズの最上階がうらやましくなるほど笑)
たとえばアリも蝶々も、自分がその虫と関わらなくてもいい「自分の外」(蚊帳の外)で見るぶんにはそこまではこわくないんです。「こわい!!」となるのは、自分が蚊帳の外ではいられなくなったとき。その虫と関わらなきゃいけなくなったとき。
ここ、小田原に越してきたのは真冬の2月で、虫たちとはまだ他人の関係でした。春になり、、草木たちの生長のはやさに驚くとともに、草木のそばで生きる虫たちと他人ではいられなくなった。
畑や果樹、草花、庭木の手入れをするときや、外周や庭の雑草を抜いたり、草木の剪定をするとき。葉っぱに青虫だったりナメクジだったり、アブラムシ、ダンゴムシ、ヨトウムシ、アザミウマ、コナジラミ、クサギカメムシ、カイガラムシ、etc……の虫たちがいたりするわけです。
頭上には蝶や蜂、足もとにはアリにヤスデ、、、虫がこわい者からしたら泣きべそだけでは済まない「こわいこわいワールド」です。
こわいけど、やるしかない
でも、ほおっておくわけにはいかない。
やるのは、わたし(まりんさんも虫がこわくて、彼女の場合、そのこわさが皮膚に影響してアレルギーが悪化しちゃう。だからといって、そのたび業者さんにお願いするだけのお金はない。虫が平気な友だちはいてもそのひとはスーパーマンじゃない。わたしがやるしかない!)。
特にこわかったのは、草木が茂っている建物脇の通路と、庭のすみっこのジャングル地帯(←とんでもなくオーバーな表現なんだけど、ぼうぼうと生い茂る草木でその先が見えないのがジャングルみたいに思えて、それぐらいこわいの!!)。
フル装備して、二の腕までの手袋をはめて、長靴をはいて、ゴーグルにマスクもつけて、いざ出陣!
まりんさんは「がんばってー!」と、10メートルほど離れた所、窓を閉めた部屋のなか、などなどから応援しつつ見守ってくれている。
以降ほぼ毎日のように、フル装備で、草を抜いたり剪定したりしているのだけど、日ごとにこわさが和らいできています。
恐怖は立ち向かわずに和らげていく
で、思ったんです。(ここからが本題。前置き長くてすみません^^;)
よく「恐怖を乗り越えろ」とか「恐怖に立ち向かえ」って言うけれど、恐怖に立ち向かうんじゃなくって、恐怖が少しでも和らいだらそれでいい。
こどもさんが不登校をするようになって、他人事ではなくなった親さんが「こわいよー! どうしたらいいの〜」となったとき、そのこわさを和らげてくれる安心アイテム(安心毛布みたいなもの。わたしの場合は、手袋や長靴のフル装備)があればいいなあって。
学校の先生や校長・教頭と話をしなきゃならなくなった、「こわいよー!! どきどきするよ〜」なんて時もそう。
恐怖が少しでも和らいだらいい。恐怖に立ち向かう方法じゃなくって、恐怖が少しでも和らぐよう、恐怖に対する備えを知っていたらいい。
恐怖は人間の基本的な感情だから、恐怖を消すには? と考える必要はなくて、そもそもできることではないです。「うれしい」や「たのしい」の感情と同様に、「こわい」の感情も、なくてはならない大切な感情です。
人それぞれ、時それぞれ、度合いもそれぞれで、いろんな「こわい」があります。
強すぎる恐怖のもとでは、思考は停止するし、体も動きません。体は動くけれど冷静な判断ができない、そんな恐怖もあります。
で、今回のわたしの経験からわかった「恐怖を和らげる3つのステップ」が、これです。
[box class=”blue_box” title=”恐怖を和らげる3つのステップ” type=”simple”]
- 感情を適切に認識し、正直に迎え入れる
- 準備を万端にする
- 信頼できる人に頼ることをやめない
[/box]
これは冷静な判断ができる、思考して悩む余地のあるときのこわさに対するものです。
(もちろん、冷静な判断ができる恐怖への対処方法なんて、個人・時・場合によって異なります。自分に合うものが自分以外の人にも機能するとは限らないので、参考程度にね。)
① 感情を適切に認識し、正直に迎え入れる
まずは、こわい感情を適切に認識するところがスタートです(「適切に認識する」をしないでいると、やみくもにこわがってしまい、冷静な判断ができず、「不安」も湧き上がってきてしまいます)。
そして正直に、そのこわい感情を迎え入れます。
今回のわたしの場合だと「虫がこわい!!」なんだけど、こわいの感情を受け入れるのって、簡単そうでいて簡単じゃなかったりするんですよね。
たとえば「こんな歳してアリがこわいだなんて情けない」とか、男性の場合だと「男のくせに虫がこわいだなんてカッコ悪い」なんてこともあるかもしれませんね。「親としての面子が立たない」「それでよくもまあ庭がほしいなんて言ったよな」etc……とにかく、わたしたちは自分をジャッジしまくります。
自分が自分にジャッジをくだして、自分を痛めて自分をまもります。誰かに「そんなことないですよ〜」と言ってもらえることを期待もします。
(ちなみに、他者から「そんなことないですよ〜」と言ってもらいたい期待をもつと、もともとの「こわい」に加えて、言ってもらえるかな、どうかな、といった「不安」が加わります(「不安」には「期待」が潜んでいる)。で、仮に誰からも「そんなことないよ〜」と言ってもらえなかったら? 感情は「怒り」をも含んだものになっていきます。
シンプルに「虫がこわい」だったのが、「そんなことないよ〜」と言ってくれなかった人への攻撃の気持ちになったり、拒絶になったり。そんな自分にうんざりしたり。。。はじめの「虫がこわい」の感情はどこ行ってーーん笑。)
恐怖は大事
あるがままを受け入れる、そんな単純なことを難しくさせてしまう原因には、こども時代の親との関係や学校をはじめとする環境も影響していると思います。
こどものとき「虫、こわい!!」と言うと、「えーーなんでぇ? 虫なんてこわくないよ〜」と否定されたり、「なに言ってんの、たかが蚊でしょ」「男の子でしょ」「これだから今時の子は……」「虫だって生きてるんだよ」「そんなこと言ってたら何もできないぞ」とかとかね。数えればキリがありません。
オバケがこわい、トイレがこわい、、、ほんとにこわかったのにな。
学校の先生や校長にお話しするのがこわいのだって、「ちゃんと(親や先生に)わかるように話しなさい」「あなたの言ってることわからない」「目上の人に逆らうんじゃない」などなどと、聞く耳もたない大人にさんざん言われてきているんです。
結果、「話す」のがヘタだって思い込んでいたり、苦手になったり、、そうなるのも当然だよね。
恐怖を感じることは重要なんです。
恐怖は本能。だからそれをジャッジしたり拒否したりすることなく、こわい感情を適切に認識すれば、不安や期待・怒りといった今はお呼びじゃない感情に振り回されることなく適切に恐れることができます。
小さな年齢のこどもが、教えられてもいないのに、前を向いて階段をおりるのはこわいから、這って後ろ向きで降りていくのもそうですよね。本能に添う彼・彼女たちは自虐的なことを言ったり、自嘲したりはしません。
そして、(めだかの学校をそぉ〜と覗くように)恐怖のなかみをじぃ〜と覗いていると、「こわい」の感情は警戒や用心、洞察といった活動へと発展していくのがみえてきます。これって、つまり「希望」じゃないですか。
② 準備を万端にする
つぎに、書籍やインターネット等から情報・知識を集め、具体的な準備をしていきます。
虫がこわいわたしの場合だと、蜂もいたので白っぽい服類や小物、剪定ばさみや柄のなが〜い高枝切鋏などの道具も揃えました(高いところの木の枝を切るためだけでなく、目の前の草木と最大限のキョリをとれるので大活躍!)。
草木のなまえも知っていきました。あと、虫も! どんな虫がいるのか、さっき見た虫はどんな虫なのかを調べるために、おそるおそる、こわい画像(ヤスデとかヨトウムシとか)もがんばって見た!
PTAの退会、給食のストップ、学校の先生になにかをお願いしたいときは
たとえば PTAの退会 など、学校の先生になにかをお願いしたいけどお話しするのがこわいときだったら、自分なりのレジュメを作ればいいですね。
紙とペンでも、スマホやPCでもいいけれど、書いては考え、考えては書き、やり直し、また考え、ウンウンとうなりながら(笑)書き出していく。
文献を参考にしながら、伝えたいことを大枠からだんだんと分解していき、最終的に要点・必要事項などを簡潔にまとめ上げていきます。
そしてできあがったものを、先生に伝わるか? 主張と根拠はしっかりつながっているか? 抽象的な言葉はないか? 論理的になっているか? 失礼はないか? といったふうに見直していけばいいと思います。
(具体的な物事をお願いしたいとき、抽象的な言葉だと、自分が伝えたいことと相手がする解釈にズレを生んでしまいます。なので、言葉は具体的にしましょう。パートナーやこどもになにかお願いしたいとき、解決したい問題を話すときも同様です。)
>>> 関連記事
不登校への対応の要望がスンナリ通る人に共通するのは何か?
安心毛布のような、恐怖が和らぐ安心アイテムっていうのは、この「準備する」の内にあると思うんです。
今回のわたしの場合だと、恐怖を和らげてくれた安心アイテムは、手袋でした。
また、学校との関わりはこどもたちの卒業とともに終えたけれど、いまでもいつでも、たとえば役所へなにか尋ねるとか、税務署に電話で問い合わせるなんてときは、要件を簡潔にまとめたメモを作ります。
で、深呼吸して電話しています。この事前準備は電話嫌いのわたしにとっては必要で、恐怖が和らぐアイテムでもあります。
これは補足ですが、学校のほうから「お話しがある」と言われたり、突然質問されたりってこともあると思うんですね。
こんなときもわたしは、相手から訊かれそうなことをありったけ想定しておきます(たとえば社会性についてどう考えてるのか、集団行動はどうかとか)。いろんな本を読んで勉強して、法律を調べて、伝え方を考えて、、メモを作っていました。
わたしが「A」と答えたら、想定できる先生方の返答パターンを考えて、「い」だったらこう、「ろ」だったらこう、「は」はこう、なんて具合で。この勉強は、物事をみる視点や捉え方をひろげてくれたなあって、いま思います。
③ 信頼できる人に頼ることをやめない
信頼できる人がそばにいてくれると、恐怖は和らぎます。これはもう絶対!
こどもが日々にあたらしく、一歩先に明日へ踏みこんでいけるのだって、親を信頼しているからです。
信頼している親が、振りむけばいつだってそこにいてくれているから、だから安心して毎日冒険に出かけられる。「ただいま」「おかえり」がくりかえされる。
おとなになって物理的には隣にいなくても、信頼できる家族や仲間、手をぎゅっとつないでいてほしいときに、ぎゅっとつないでくれるひとがいるというのは、ほんとうに、ほんとうに、こころ強いものです。
[box class=”yellow_box” title=”よっぴー・まりんのオンラインコミュニティ「お母さんのじかん365」”]よっぴー・まりんのオンラインコミュニティ「お母さんのじかん365」では、子育て、子育ちってどういうことだろう? 学校ってなんだろう? と立ち止まって考えている、共感しあえる親さんたちとオンラインでつながっています。
>>> 関連記事
・嫌いな人を慮る — 「先生である前にひとりの人間」ではなく、ひとりの人間が先生であり親であり子であるということ
・お金で買えないクリスマスプレゼントを子どもがサンタクロースにお願いしていたら、親はどうする?
[/box]
今回、わたし以上に虫がこわいまりんさんが、10メートルほど離れた所や、窓を閉めた部屋のなかから「がんばってー!」と応援してくれていて感じたのは、上等な絹のスカーフみたいな心地よさでした。
蚊帳の内の者みながこわいと感じる出来事が蚊帳の内で起こっているとき、自分にとって(ここではまりんさん。読んでくださっている方に対しては親の方)、適切に恐れることができるめーーーいっぱいの最短距離にいてくれている、その気持ちよさ。肌触りがやわらかくて、濡れた綿のようなずしっとした重さがない。
わたしがこどもだったとして、学校に行けなくなったとして、そのとき親にはこんな塩梅でいてほしいなあと感じたのでした。見守るってこういうことなのかなあって思ったのでした。
暑いときは涼しく、寒いときは暖かい絹だったら、いらないときは丸めてポケットにつっこんでおけるし、持っていても軽いしね。
適切に恐れることができない距離まで近づくと(近づかれると)、どろっと重たい。親と子の関係が、信頼の反対側、嫌悪になってしまいます。 頼りたいのに、頼れなくなってしまいます。
親は軽いに限るのです。
まとめ
「こわい」をジャッジする必要はありません。なくてはならないものだし、いま「こわい」と感じているのはホントなんです。「こわくない」なんて嘘をつかせてはいけない。
恐怖を乗り越えなくていい、恐怖に立ち向かわなくていい。恐怖が少しでも和らいだらそれでいい。和らげてくれるアイテムをたくさん身につけて、自分の「こわい」も相手の「こわい」も否定しないでいよう。