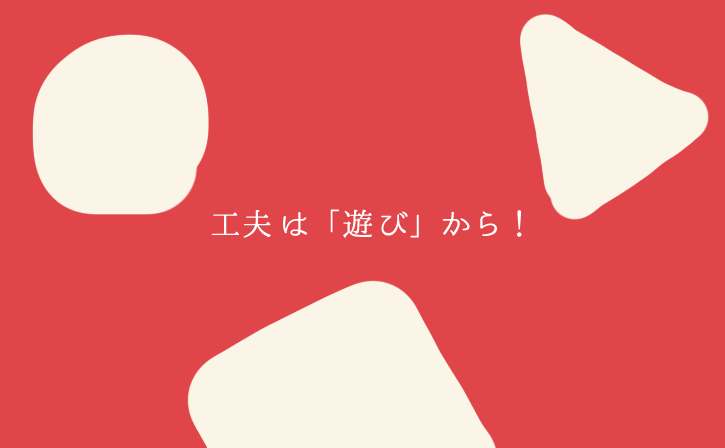こんにちは、
こどもの「学校に行かない選択」を担任などに伝えると、反論をされて萎縮してしまったり、スムーズに受け入れてもらえなかったり……ということがありますよね。
小中高に通わなかったまりんと、母親であるよっぴー、わたしたちのおもう、「学校に行かない選択」を伝える3つの心構えと、そのために必要な「遊び」について書いています。
もくじ
先生がわかってくれないとき
こどもが学校に行かない選択をすると、親はその旨を学校に伝えることになります。
このとき、担任の先生や校長先生、学校側がすんなりと頷いてくれることもあれば、難色を示されることもあります。
むしろ、後者の経験をされた方・されている方のほうが多いんじゃないでしょうか?
厳しくであれ穏やかであれ、反論をされて、バトルのようになってしまったり。
保健室登校や放課後の登校などの提案を受け入れざるをえなくなったり、関係がギクシャクしてしまったり。
学校は良心から、「不登校」はこどものためにならない、そもそもあなた(親)の教育が……などなど、ようするに「学校に行かないことは問題」で、「“普通に“学校へ通える」ように、(学校側にとって)正しい道へ戻そうとします。
(「不登校」は、こどもに問題があるのではなく、そのこどもに適応しない現在の学校制度に問題があります。
関連記事 >>> 不登校が苦しくない親の特徴は「知っていること」)
そんなとき、学校に行かない選択を、担任(学校)にはどう伝えればいいのか?
小中高に通わなかったまりんと、母親であるよっぴー、わたしたちのおもう、「学校に行かない選択」を伝える3つの心構えをお伝えします。
そして、そのために必要で大切な、「遊び」について。
「じゃあどうやって?」は楽しい遊び
学校に行かない選択にかぎらず、「どうすれば伝わるか?」「どうすれば伝えられるか?」は、
- どうすれば商品が売れるか?
- どうすれば高得点がとれるか?
- どうすればもっとおいしいごはんが作れるか?
- どうすれば筋肉がつけられるか?
- どうすれば本を早く読み終われるか?
などなどとも同じプロセスを含んでいます。
つまり、目的と、自分なりの定義にもとづいて、「工夫をする」ということ。
ある一つの「やりたいこと」(今回の場合は「学校に行かない選択を伝える」)をやり遂げるまでの工程において、「じゃあ、どうやって?」を考えることは、本来、いちばんと言ってもいいほど、楽しい部分です。
おままごとをするこどもたちにとってのママ役、ヒーローごっこをするこどもたちにとってのヒーロー役。それくらい、楽しいところ。
でも、わたしたちはつい、「じゃあどうやって?」の答えを、他人に求めてしまう。
工夫する・考えるプロセスをすっ飛ばして、外注してしまうんです。
この積み重ねが、学校にこちらの判断を伝えてもうまくいかない、その原因のひとつです。
指示は暮らしのなかで積み重ねられる
工夫すること、考えることは、遊びなんですよね。考える遊び。
今日、わたしたちがふたりで台所に立っていたとき、「レタスを手濡らさずに洗うにはどうしたらいいんだろ?」って場面があったんです。
そんな、小さな小さな、どーでもいいような日常の場面で、多くの親は「こうしたらいいよ」とか、「こうしなさい」と指示をしています。
言われたこどもも、「あ、そうなん」と、特に違和感もなくそれに従う。
親もこどもも、指示というほど大したことだとは思っていません。そこには怒るも怒られるもなくて、こども自身の学びを奪っているなんて意識もない。
それが幾度も繰り返されていくと、「◯◯はこうする」になって、「工夫、考える」の工程がなくなっていきます。
あらゆる物事について、暮らしのなかで、こうして積み重ねられています。
親は先回りをしてしまう
たとえば、忘れ物をしてしまったときの「じゃあどうするか?」もまた、おもしろい「遊び」です。
でも、親はつい先回りをして、「忘れ物をしないように」する。
忘れ物をしなかった子がマルで、した子はバツ、そういう染みついた「決まり」があるからです。
だから、前の日の晩や、当日の玄関先で親がチェックをして、「忘れ物をしないこども」をつくっていく。
もちろん、忘れ物をすることがマルで忘れ物をしないことがバツ、なのではありません。
そうではなく、親の先回り、つまり干渉によって、こどものなにが奪われているのか? です。
「“考える”遊び」がなくなっている、という見方をしてみる。そこからじっと見つめてみると、無数にある方法や感じかたを一つの枠に押しこむことがいかにもったいないか、いかにこどもの力を奪ってるのかも、わかってきます。
でも、奪っているほうも奪われているほうも、そんなことには気づかない。
そんな積み重ねが「じゃあどうするか?」「どうやって?」の部分を、朝から晩まで、奪っていく。
結果、「どうすれば伝わるか」についても、「考える力」が育たず、誰かに答えを求めてしまう。
そこには恐怖があります。「これで間違っていないか?」「これで正解か?」、と。
自分の好奇心にそった勉強
「遊ぶ」は、答えが決まっていない・終わりも決まっていない・方法はひとつではないもの。
この「遊ぶ」が、とにかく必要なんですよね。だからこそ、たくさんたくさん、ひとつでもたくさん遊んできたひとは、この「どうやって?遊び」も得意になっていきます。
LINE@ には近ごろ、「学校がはじまるけど宿題やってない、どうしよう」といったメッセージもたくさんいただいています。
これもまた、学習指導要領にそって、答えの決まっている(これが正しいというゴールが設定されている)勉強をしてきたことによる、ある一面から見た弊害なんですよね。
学校基準の成績や点数の低い・高いではなく、自分の好奇心にそって勉強をする経験は、原石を磨いていくことです。
じゃあ、その経験の多くない大人は、こどもの「学校に行かない選択」を担任の先生にどうやって伝えればいいのか。それを、どうやって考えるのか?
学校に行かない選択を伝えるための3つの心構え
こどもの学校に行かない選択を伝えるための3つの心構え。
これは、担任の先生にわかってもらえないのでは、と不安になるときも、実際にわかってもらえなかったときにも。あるいはほかのどんな内容を伝えるときにも、役に立ちます!
>>> 関連記事
不登校への対応の要望がスンナリ通る人に共通するのは何か?「攻撃型」「ひっこみ型」「率直型」で分かれる
不登校のとき担任からの電話でやってはいけない注意点
「学校に行かないで将来はどのようにお考えですか?」とカウンセラーの先生に尋ねられて
① 自分の望みを把握する
自分はなにを伝えたいのか? がはっきりしていることが大事です。
まずは以下の3つを、箇条書きで考えてみましょう。
[box class=”blue_box” title=”言語化してみよう” type=”simple”]
理由 … こどもが行きたくないといっている、ほかに好きな学校がある、公教育には疑問を抱いている、コロナの不安があるから、etc
その理由による自分の判断 … 行かない、行かせない、休む、etc
今後の要望 … 登校や行事のお誘いは不要、家庭訪問はいらない、教科書はほしい、etc
[/box]
この段階では、建前やウソは厳禁です(自分についているウソも含めて!)。
まず、ちゃんと「自分」を把握しましょう。
② 担任の先生とは、ひとりの人間として向き合う
「学校側にとって、言われてうれしいわけではないだろうと思うこと」を言いきることに恐怖やためらいがあって困っている方もいるし、
恐怖がなく言いきってしまうからこそ学校との付き合いがうまくいかない、という方もいますよね。
ここからは、建前も方便です。
① で書き出した「理由」「判断」「要望」を変えることなく、簡潔に伝えられるように考えます。
そして、担任の先生は、担任の先生であると同時に、ひとりの人間です。悪意や攻撃性を感じると、誰でも、好意的な反応は返せません。
下手に出る必要はありません。
あくまでひとりの個人と向き合うというイメージで、好意をもって、相手の性格、性別や年齢、考えのタイプ、などなど、相手に合わせて伝え方を考えましょう。
③ 相手を変えようとしない
「どうすれば伝わるか」は「どうすれば要望を受け入れてもらえるか」ということですが、これと「どうやったら相手を変えられるか」は、まったく別ものです。
学校に行かない選択をするために、担任、先生や校長にわかってもらう必要はないし、変わってもらう必要もありません(理解してくれる方に出会えたらラッキー!)。
もちろん、学校に行かない選択に興味・関心や共感をもっている先生もいらっしゃいますが、まったくその気もない相手に、「理由」を理解してもらおうとするのは、無茶で、横暴なことです。
ほんの数年間のお付き合いです。ただ「判断」と「今後の要望」をそのまま受け取ってもらえれば、それでいい。
どうすれば「遊ぶ」人になれるのか
「遊ぶ」をさせてもらえなかった・してこなかった大人が、その工夫ができるようになる方法はひとつです。
それは、「遊ぶ」をし続けてきた・し続けている人と、長く一緒にいて、その環境に身をおきながら肌で学ぶということ。
>>> そんな場をつくりたくて、物件とスポンサーを常時募集しています! 詳細はこちら
デモクラティックスクールとゲストハウスを足したようなおうち「デモクラティックホーム」を大阪でつくる!
でもこれは、それぞれの生活があるなかで、いつでも誰でもできることではありません。
いまから親ができることは、自覚をして、せめてこどもからはその力を奪わないようにしよう、と決めることです。
そうしたら、こどもは遊びを、勉強を、学びを続けていく。
幸運なことに親は、こどものすぐそばで、その姿から学ぶことができるんです。
[box class=”yellow_box” title=”「オヤトコ学校 いい舟」ではこんなことを学んでいます” type=”simple”]よっぴーまりんが主宰するオンラインスクール「オヤトコ学校 いい舟」は、こどもとヨコの関係になるための学びの場です。
たとえば育児書を読んで子育てをすることがあるけれど、育児書に、いまともに暮らしている「わたし」と「こども」の関係のことは書かれていません。
「オヤトコ学校 いい舟」では、答えやハウツーではなく、目の前のこどもと、わたしとの関係を紡いでいくために、まず親自身が自律をとりもどすところからはじめていきます。
ひとつ屋根の下で暮らす家族、その誰もが心地よく暮らしていける家庭をみんなで築いていきましょう。
「オヤトコ学校 いい舟」の 詳細はこちら
→ https://ai-am.net/iifune1127
[/box]